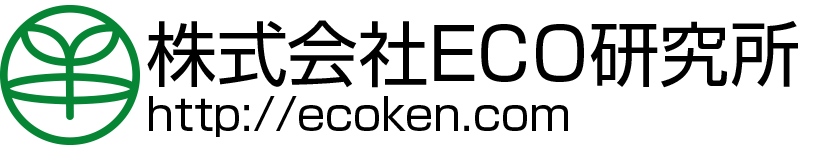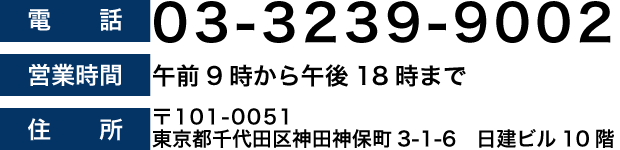『環境時々刻々』vol.03
日中間の緑化事業が本格的なきざしを見せたのは、
1999年の小渕内閣の時代。
100億円規模の「日中緑化交流基金」が設立されたことにより、
それまで行われてきた団体や事業者による細々とした
自発的な緑化運動が、安定的な継続をみせるようになりました。
それを遡る15年ほど前(1985)には国際森林年が制定され、
ブラジル奥地アマゾンの森林伐採など、
国を越えた様々な環境問題に光が当たり始め、
環境保護の意識が胎動を始めた頃の話です。
亡くなった後も、今なお多くの中国人に砂漠緑化の祖と認められている
一人の日本人遠山正瑛氏が、黄河流域の乾燥地でブドウの栽培に
成功し、ここから日本人の協力による中国の沙漠の緑化運動が
静かに動き出しました。
1990年代には、いくつかの民間団体がつくられ、
日本人による内モンゴルや黄土高原の緑化運動はゆっくりと力を
伸ばしていきました。
かつて日本でも、1950年代の朝鮮戦争への軍需や、
その後の経済発展(資源や燃料の開発・建築資材としての木材伐採、
宅地や工業地の開拓)などで多くの森林が失われてきたように、
中国でも日本に遅れること10年して始まった経済活動の隆盛の結果、
この20~30年の間に当時の日本を遥かに上まわるスピードで
多くの森が消え、同時に、黄河流域の水害や砂の引き起こす
大きな災害が目につくようになっており、
それは今も続いたままです。
気象庁(日本)の黄砂観測記録を見ても、1988年を境に
それ以前の20年間に観測された日数に対し、恒常的な増加を
みせており、2002年・2010年には日数・観測地点数を勘案した
延べ日数とも、それまでの平均の2倍強を観測しています。
「地球」という星を、こうしてひとつの生命体として俯瞰してみると、
中国やモンゴルの砂漠化は決してその狭い地域のこととは
考えられません。
ただし、すべてが上手くいっているかというと、
必ずしもそうとは言えないようです。
かつての侵略国家「日本」に対しての憎悪があったり、
遊牧を礎とする民族が、農耕地を増やすために
農耕系民族に半ば強制的に移動させされたり、
成長途上の樹木を抜いて薪にくべたり、何一つ緑が無い状態で
活動の趣旨とその結果とを理解をさせることに苦労したりと、
様々な労苦と同時に、緑化の技術そのものの変遷・変化も
起こっているようです。
生育の早い樹木のみを植林することで、地下水脈が一層低下して
しまったり、水分蒸発量の多い広葉樹を植えることで、
むしろ地域の水不足を招いてしまったりと…。
今では、現地従来種である「沙柳(サリュウ)」「烏柳(ウリュウ)」
「楊柴(ヤンチャイ)」など、比較的水分蒸発の少ない
低木性の植物を用いた飛砂防止策をとるところから始められています。
また、数年ごとに刈り取ることによって大きく成長する
「烏柳(ウリュウ)」については、その刈り取った枝がパルプとして
紙の原料になるなど、現地の方の参加が基本の、
持続的活動としての役割も拡げているようです。
それでも砂漠化は、なお拡大を続けているのです。
もし、中国の地図を広げたり、グーグルアースなどをお使いになられた
際は、そんなことを片隅に置きながら、覗いてみてください。
次回からは、少しクルマに関連する話へと舵を切っていこうかと思います。
文責 T.ま のすけ